
「人生ここから」を考える 大人のためのヒントが見つかる場所、というキャッチコピーのウェブサイト、「朝日新聞Reライフ.net」に寄稿しました。よろしければご高覧くださいませ。
今回は「ねんきん定期便」をキーワードとした記事です。
私の金融資産残高の推移を3カ月ぶりに点検しました。
[3カ月前の記事を複製し、表やグラフを更新した上で、更新した文字列を赤にしています。お急ぎの方は赤いところだけお読みください。]
この記事における「金融資産」の前提:
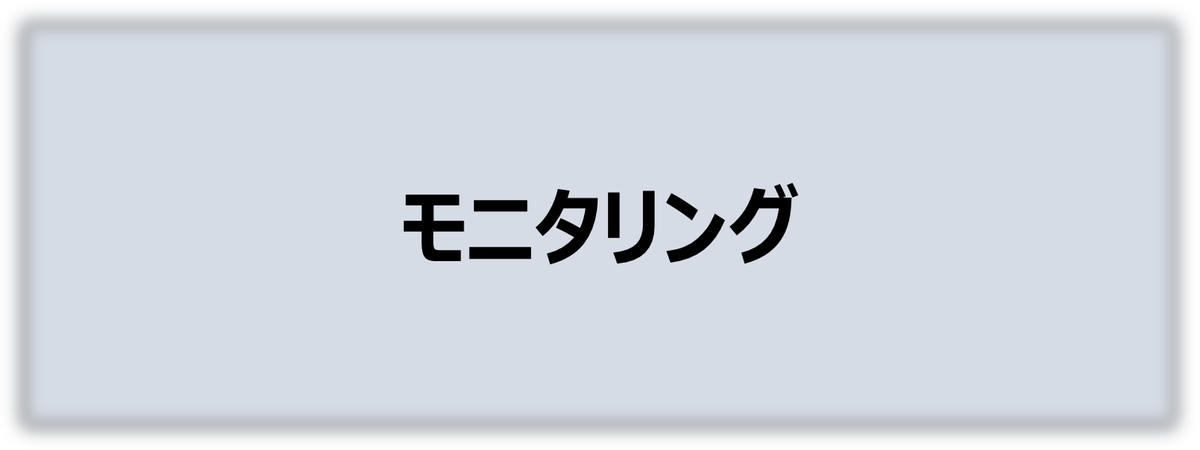
2001年からさまざまな投資・投機を試行錯誤し、数々の大失敗を経験。リーマン・ショックをはじめ、紆余曲折を経て私がたどり着いた投資手法は、
です。私はこれを資産運用の中心・中核(コア戦略)とし、「分散・節税・低コスト投資」と呼んでいます。
成果を感じ始めたあと、理論的な裏付け・確証を得るため資産運用に関連する資格を取得したり、偶然、年金基金の運営に携わることになったりした結果、「一般個人の金融資産運用と年金基金の年金資産運用は、税制や金融商品の違いを除けば本質的には同じである」という結論に達しました。
プロ向け(機関投資家向け)資産運用ビジネスの業界では、「年金基金による年金資産運用が資産運用の標準的な方法」とされています。であるならば、一般個人も年金基金の運用基本方針を理解した上で資産運用する方が良いと思いませんか?
「分散・節税・低コスト投資」は、
という考えに基づき、
という、単純かつ手間のかからない投資手法です(実際には買い増しだけでなく、節税と乗り換えの目的で売却することもあります)。
私の運用目的は「老後資金形成」です。「長生きしたい」とか「(金銭的な意味で)贅沢したい」などの気持ちはないのですが、「将来、自分または配偶者が想定以上に長生きしてしまってもお金に困ることがないよう、無理のない範囲で準備しておきたい」、ただそれだけです。
アセットクラス別のグラフとベンチマーク別のグラフです。それぞれ前年同期と比較します。
前年同期の
今回の
前年同期の
今回の
前述の「1. 私の投資手法(分散・節税・低コスト投資)」です。
リスク資産(投資信託)は、SBI証券の特定口座とNISA口座に置いています。もともとは、直販投信を含め、複数の金融機関で投資信託を運用していましたが、管理の手間を減らしたかったことと、良質な投資信託をひととおり取り扱っていることから、2011年までにSBI証券1社に集約しました。
以下、特定口座とNISA口座における本年分の運用損益を「トータルリターン」で確認してみます(iDeCoは含まれません)。
SBI証券における年間トータルリターン


コア戦略以外の取引や保有分をサテライト戦略と称しています。
| 内容 | 実現損益 (税引前) |
現在の運用状況 |
|---|---|---|
| なし |
【金融資産7000万円台を回復】
レバレッジをかけた資産や外貨建て資産を含めたこれまでの運用成績を、まとめて(1枚で)お見せする良い方法を思いつきません。そこで、収入や支出、負債の返済、リスク資産の値動き等々、私のすべての経済的活動の結果である「金融資産残高の推移の棒グラフ(月次)」を掲載します。

1本の棒の高さは、その月の
の結果としての、月末時点の金融資産残高を表しています(負債を差し引く前の残高[いわゆるグロス、総額]であり、純金融資産残高[いわゆるネット、純額]ではありません)。
以上、参考になるかどうかわかりませんが、会社員世帯の実例として投稿しました。
昨日、日本経済新聞から「iDeCo掛け金、70歳未満まで 厚労省が5年延長方針」という特報が出ました。

2022年11月28日に新しい資本主義実現会議が決定した「資産所得倍増プラン」においては、「第二の柱」として「加入可能年齢の引上げなどiDeCo制度の改革」が明記されていました。いよいよ2025年の法改正を目指した動きが本格化します。
上限額引き上げの方は「決め」の問題だと思います。必要以上に公平性に気を使った結果、働き方や勤務先によって掛金の上限額が異なるこれまでの複雑な仕組みを改め、NISAのようにシンプルに、全員一律の上限額になることを希望します(加入のハードルを下げるためにも、公平性より、わかりやすさを重視すべきでは、という意見です)。
難しいのは加入可能年齢引き上げの方でしょう。現状は「65歳未満」ですが、実際には「国民年金の被保険者であること」をはじめ、さまざまな要件を満たす期間しかiDeCoに加入できません。「70歳未満」に引き上げるとなると、一部の会社員などを除いた60代後半の多くの人は、すでに国民年金の被保険者ではなくなっています。65歳を超えて加入可能年齢を引き上げるには、「iDeCoを含む私的年金は、公的年金の上乗せの制度である」「iDeCoの加入対象者は、国民年金の被保険者(の一部)である」という根本的な建て付けを見直す必要が出てきます。
65歳以降の具体的な加入要件について、厚生労働省が公開した意見を以下に抜粋します(2024年2月27日「第32回 社会保障審議会 企業年金・個人年金部会」資料より)。
個人的な賛否としては次のとおりです。
今年は5年ぶりに財政検証が行われる年ですので、来年にかけ、年金制度関係のニュースが増えるでしょう。
昨日、令和5年分の所得税の確定申告を完了しました。

今回もあれこれ試さず、次の手順と方法です。
このブログに何度か書いてきたように「確定申告書等作成コーナー」は毎年改善されていて感心します。
今回も便利だったのが「マイナポータル連携」ですが、私の勤務先が昨年分の年末調整から一部の保険会社のxmlに対応し、それを利用した結果、
①勤務先の年末調整で、xmlをアップロードしたもの
②勤務先の年末調整で、書面を添付したもの
③マイナポータル連携で取得できるもの(①の全部と②の一部を含む)
が混在することとなり、便利な反面、重複させないための確認作業が増えてしまいました。
なお、今回の改善の目玉は「給与所得の源泉徴収票もマイナポータル連携できるようになった!」ことだと思うのですが、残念ながら私自身は連携できませんでした。会社(人事)としては、「年末調整の利便性向上は自分たちの仕事だが、確定申告は管轄外」ということなのかもしれませんね。

「人生ここから」を考える 大人のためのヒントが見つかる場所、というキャッチコピーのウェブサイト、「朝日新聞Reライフ.net」に寄稿しました。よろしければご高覧くださいませ。
今回は「退職金なし」をキーワードとした記事です。